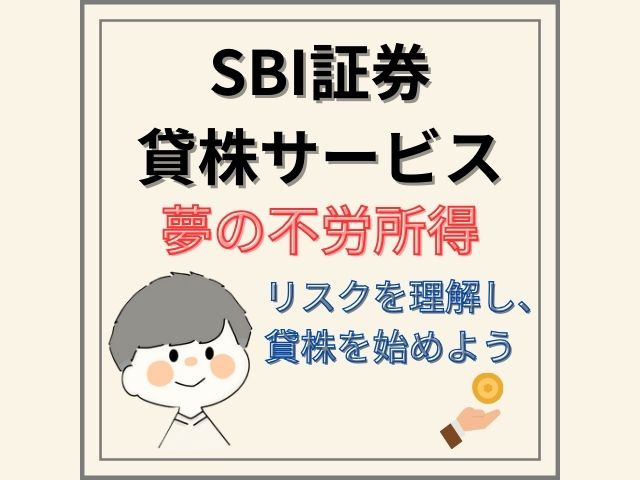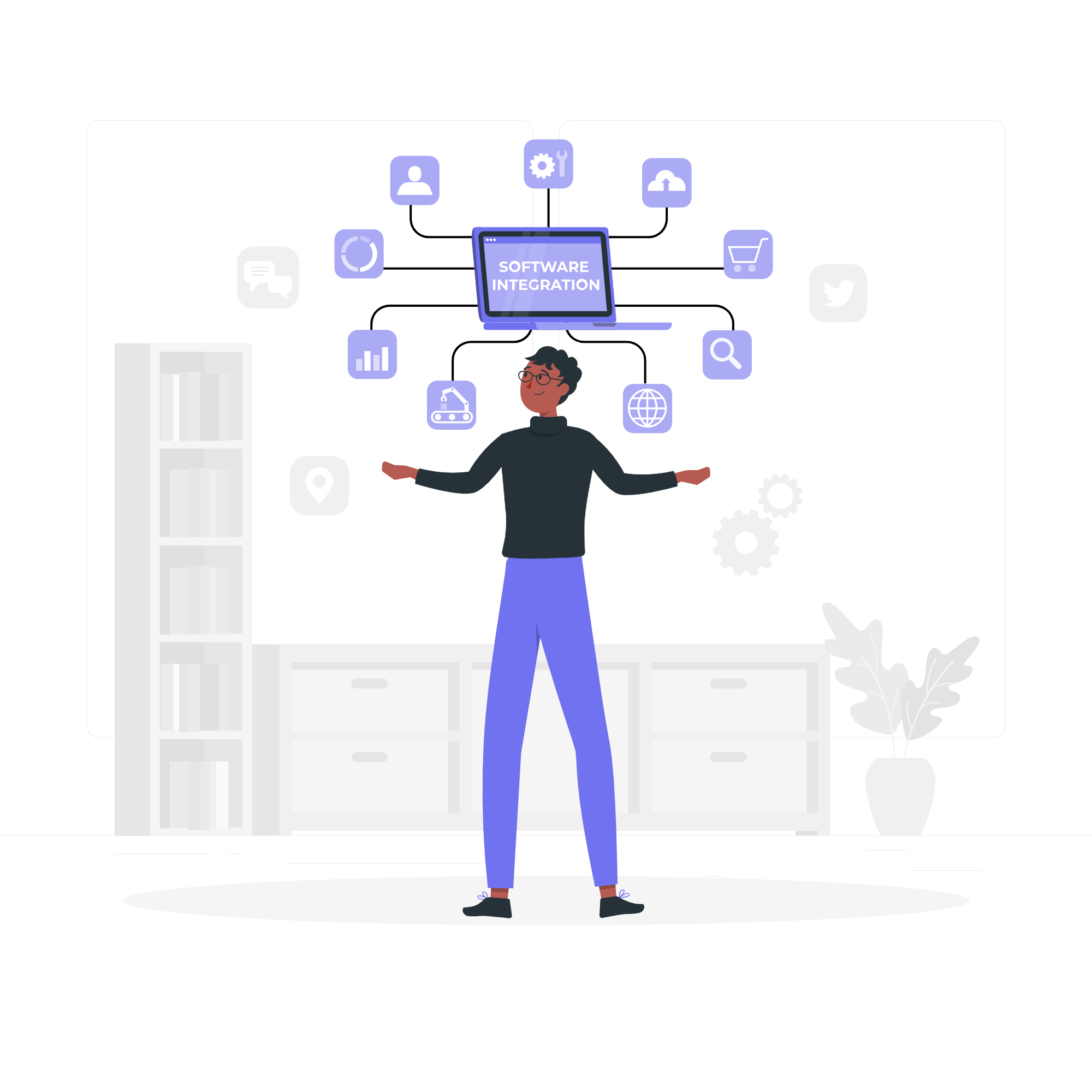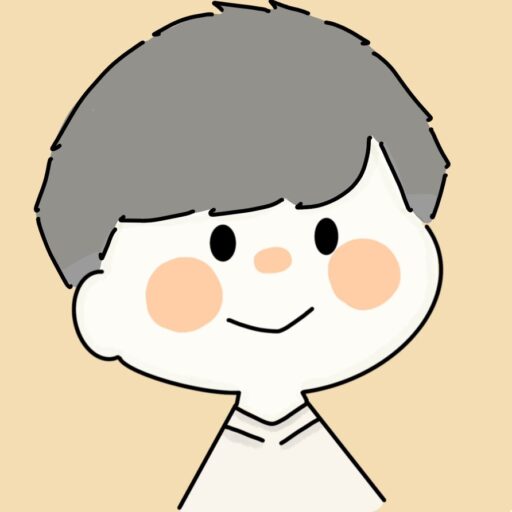皆さんこんにちは!

こんな悩みに答えていきます。
2023年1月14日にSBI証券の貸株制度が拡張され、より素晴らしいサービスとなりました。
そんなSBI証券の貸株制度について徹底解説していきます。
これから貸株を始めようと悩んでいる方、貸株について理解したい方、ぜひ参考にしてください。
それではいきましょう!
この記事の内容
- 貸株について
- 貸株のメリット
- 貸株のデメリット
- 貸株と配当控除は併用可能か
- 貸株は確定申告する必要があるのか
SBI証券 貸株制度拡充
先に、本記事の結論を記載します。
本記事の結論としては、「貸株のリスクを把握した上で実施すべき」です。
2023年1月14日にSBI証券の貸株制度が拡充され、貸株はより使いやすくなりました。

貸株とは?

貸株のメリット・デメリットを説明する前に、貸株とはそもそも何なのか。
こちらについて解説します。
貸株とは
- 証券会社に株式を貸し出すことで、貸株金利を受取ることができる制度のこと
銘柄によっては1%以上金利がつく銘柄もあります。
つまり「貸株」とは、通常の配当金・株主優待に加え、貸株金利を受け取ることができる画期的なサービスなのです。
例えば、皆さんが配当金3%、貸株金利0.3%の株を20万円分持っていると仮定して考えてみます。
貸株としてSBI証券に貸し出すことで、「配当金6000円、優待」+「金利600円」獲得できます。
株式を持っている方はぜひやりたいサービスですよね。

貸株のメリット・デメリット
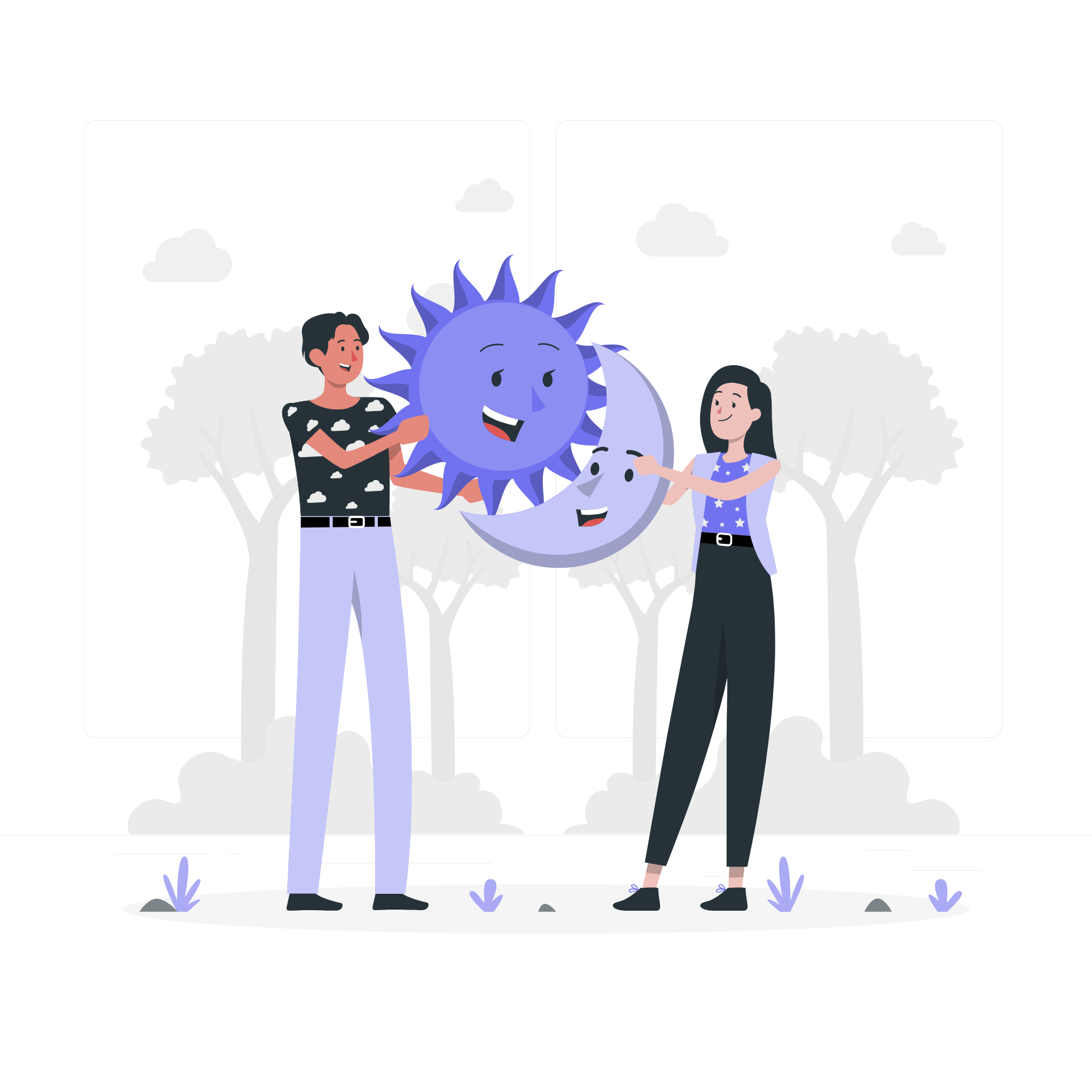
貸株について理解した上で、貸株のメリット・デメリットについて解説します。
貸株のメリット
- 金利を受け取れる
- 貸株中でも株主優待・配当金を獲得可能
- いつでも売却可能
メリット①:金利を受け取れる
SBI証券では金利の上限がないため、その時によって金利が変動しますが、最低でも0.1%~金利を受け取ることができます。

メリット②:貸株中でも株主優待・配当金を獲得可能
貸株権利を選択する際、「配当・優待優先」を選択することで、貸株中であっても「配当金」が「配当金」として受け取ることができます。
大切なので、もう一度言います。
貸株権利を選択する際、「配当・優待優先」を選択することで、貸株中であっても「配当金」が「配当金」として受け取ることができます。
なぜこれが大切なのか。それは「配当金相当額」について理解する必要があります。
配当金相当額とは
- 配当所得扱いにならず、配当控除が使えなくなるお金のこと
「配当金」を「配当金」として受け取るか、「配当金相当額」として受け取るかで、手元に残る配当金に大きな差が生まれます。

メリット③:いつでも売却可能
貸株中であっても、いつでも売却可能です。
「貸株中だから」といった手続きは一切必要ありません。
貸株中であっても、貸株としていない場合と同じで自由に株の売買が可能です。

貸株のデメリット
- SBI証券の倒産リスク
- 住民税の申告
デメリット①:SBI証券の倒産リスク
万が一、SBI証券が倒産した場合、貸株として貸し出した株が返却されない可能性があります。

分別管理とは
- SBIでの財産と私達投資家の財産を分けて管理すること
通常、私達がSBI証券で購入した株は分別管理されています。
分別管理されていることで、SBI証券が倒産しても私達の財産は(購入した株)は確実に返還されます。
しかし、貸株で貸し出した株は分別管理対象外となります。

デメリット②:住民税の申告
貸株金利として得られるお金は、税区分上「雑所得」となります。
皆様の所得にも依存しますが、一般的には雑所得が年間20万円以下の場合、住民税の申告のみ必要になります。

まとめ:貸株のリスクを理解した上で始めてみよう!

2023年1月14日より、貸株SBI証券でも「配当・優待優先」が始まりました。
株主優待や配当金の権利確定日に、自動的に私たちの口座へ株式が返却されて、株主優待や配当金を受け取ることができるようになりました。
「配当金相当額」ではなく、「配当金を受け取ることができるようになった」です。

さらには無メンテナンスで貸株を続けることができる点から不労所得の一つとも言える画期的なサービスです。
しかし、起こる可能性が限り無く低いSBI証券倒産リスクや、毎年住民税の申告作業といったことがあることも、理解しておきましょう。

これからも日々コツコツと投資を続けていきましょう。
最後まで読んでいただきありがとうございました。ではまた!